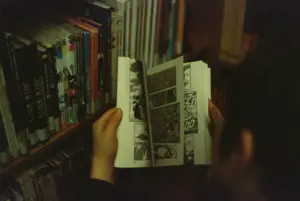Amazon、Spotify、Netflix、そして各種SNS──私たちの周囲は、日々アルゴリズムによる「おすすめ」に囲まれています。ユーザーの行動履歴や嗜好を読み取り、個々に最適化された商品やコンテンツが表示されるこの仕組みは、今やウェブプラットフォームにおける標準装備となりました。
こうした「パーソナライゼーション」は、小売業や日用品メーカーにとっても欠かせないマーケティング手法の1つです。あらゆるニーズが交錯する消費社会において、個別最適な提案は、顧客との接点を深め、ブランドへの愛着や信頼を育む有効な手段として位置づけられています。「パーソナライゼーション」は、今やマーケティング戦略の根幹を成すキーワードとなっています。
パーソナライゼーションはもはや前提条件
「パーソナライゼーション」とは、顧客一人ひとりの好みや行動履歴に基づき、最適な情報や商品を提示するマーケティング戦略です。言ってしまえば、洋服のオーダーメイドのようなもの。近年ではAIの進化に伴い、その精度とスピードは格段に高まり、ユーザーに対して“自分のために選ばれた”という特別感を提供できるようになりました。
たとえば、動画配信サービスのNetflixでは、全世界3億人以上のユーザーそれぞれにパーソナライズされた「あなたにおすすめ」欄が表示されます。音楽ストリーミングのSpotifyも同様で、ユーザーの再生履歴や好みをもとに、日々“あなた専用のプレイリスト”が生成されていきます。
いわば「パーソナライゼーション」は、顧客やユーザーにとって、購入する商品が“自分だけのためのもの”と感じられるような特別感を抱かせるための手法でもあるのです。
ユーザーが体験する「おすすめ」に対するもどかしさ
便利で魅力的に見える「パーソナライゼーション」ですが、万能とは言い切れません。むしろ、その“最適化”が逆効果を生むケースも少なくありません。
そもそも、ほとんどのユーザーは、なぜ特定の商品やコンテンツが「おすすめ」されているのか、そのロジックを知りません。そして、その違和感に気づいたときにふとこう思うのです──「なぜこれが私におすすめされるのか分からない」。
ある研究では、ウェブのプラットフォームに存在する推薦アルゴリズムがユーザーの過去の行動に基づいて人気商品を繰り返し推薦することで、同じようなアイテムばかりが表示されやすくなり、その結果としてユーザー体験が均質化される傾向があると指摘されています。
また、「自分の好みに合っている」と感じられた場合には信頼や愛着が増す一方で、逆に「なんか違う」「なぜこれなのか分からない」と感じた瞬間に、サービスやシステム全体に対する違和感や不信感が芽生えてしまう。そんなネガティブなユーザー心理が働くと、当然その行動にも影響が生じてしまいます。

Spotifyのフィードに並ぶポッドキャストの「おすすめ番組」欄に関する研究では、個別にパーソナライズされたPodcastのレコメンドが、ユーザーの視聴回数を28.9%増加させた一方で、個人レベルでの視聴番組の多様性が11.5%減少したという結果が出ています。また、全体の推薦傾向も似通っていく傾向が見られ、結果として全体としても画一化が進む側面があることが指摘されています。
つまり、アルゴリズムによって最適化された「パーソナライゼーション」は、取り入れ方を誤れば“安全で売れやすいコンテンツ”に収れんする構造をつくり出してしまう手法でもあるのです。
「パーソナライゼーション」によるレコメンドがユーザーにとっても、便利で有用なことは間違いありません。ですが、その便利さによりコンテンツの多様性が減り、画一的な体験に偏ることで、ユーザーは「またこれか……」という倦怠感を抱きやすくなります。これは、何を選べばいいのか分からないという“選び疲れ”に陥り、やがてユーザー離れにつながることもあります。
パーソナライゼーションに必要なのは「自分で見つける」体験
こうした課題に対し、ユニークな設計で応えているのがTikTokです。同社が提供している「おすすめフィードのリセット機能」は、現在の視聴履歴や学習結果を一度リセットし、再びゼロからおすすめを構築できるというもの。
重要なのは、ユーザー自身の行動がアルゴリズムに選ばれるのではなく、「自分から選び直す」行為をとれるようにしている点です。閉じかけた世界を、自分の手で開き直す余白が用意されている。これはパーソナライゼーションにおける“自律性”を取り戻す試みともいえます。
こうした“選び直せる自由”の設計だけでなく、アルゴリズムに依存しない「発見」の導線づくりも重要です。

たとえば、JINSではECサイト上で「バーチャル試着」ができるだけでなく、スタッフによる“似合い度”評価や具体的な使用コメントが添えられています。レビューにはスタッフの顔写真とスタイル情報が入り、ユーザーは「この人に似合うなら自分にも」と直感的に判断しやすくなっています。アルゴリズムだけに依存せず、“人を媒介にした発見”の導線を用意することで、ユーザーの体験にリアリティと納得感を与えている好例といえます。
レコメンドとは違った手法ではありますが、NIKEもECサイトでのスニーカー選びに「パーソナライゼーション」を導入しています。2018年から提供されているNIKEのカスタムオーダーサービス「NIKE BY YOU」(2019年にNIKEiDから改称)では、好みやサイズ、過去の購入履歴に基づいて、最適なシューズを自身でカスタマイズすることができます。
またほとんどのNike By Youスニーカーには、パーソナルiDを加えることができる仕様にしているのもユニークなポイント。こうして、ユーザーは購入商品に対して“自分だけのもの”という付加価値を感じることができるようになるのです。これは「パーソナライゼーション」の理想形の1つと言えます。
「自分ごと化」されてこそ、マーケティングは意味を持つ
便利さや最適化ばかりを追い求めるのではなく、「気づき」や「発見」といった感覚をどう仕込むか。ユーザーが“自分ごと”としてその体験を捉えられる設計こそが、これからのマーケティングに求められる視点です。
「パーソナライゼーション」は、単なる機械的な最適化ではありません。そこに人の意図やストーリー、選択肢の余白をどう残すかが鍵になります。 “人間の工夫”が加わってこそ、ユーザーの心を動かす『本当のおすすめ』が生まれるのです。
ユーザーが「これは自分のための体験だ」と感じたとき、ブランドとの関係はより強固になります。単なる効率の追求ではなく、自分ごと化される体験こそが、企業にとって本当の価値を生む「パーソナライゼーション」なのです。
Text:竹田賢治
●プロフィール
竹田賢治 / ライター、編集、Webディレクター
『Qetic』『NiEW』『WIRED』『GIZMODO』など、多数メディアで執筆。
音楽・アートなどカルチャー領域のほか、テクノロジー・ビジネス領域での記事制作も担当。