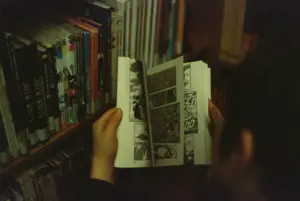「最近いい感じのキャンプ用品は?」「予算5千円で先輩の出産祝いにぴったりな贈り物を教えて」など、今や検索窓にキーワードを打ち込まずとも、AIに相談すれば要望や好みに合うアイテムをいくらでも提案してくれます。
そんな便利さが当たり前の時代となったからこそ、問い直されているのがリアル店舗の価値向上です。自分に最適な情報や欲しいものはネットですぐ手に入る中、どうすれば顧客の興味を店舗へ向かわせることができるのでしょうか。
鍵となるのは、「偶然の出会い」(セレンディピティ)です。「一目惚れして思わず……」「これを見つけたのも何かのご縁だ」「初めてだけど試してみたい」と商品を購入した経験をお持ちの方は少なくないでしょう。
そうした、AIには提供できない「思いがけない発見」を魅力的に演出し、世界的に人気を博しているのがフランス・パリ発のコンセプトストア「Merci(メルシー)」と、台湾・台北発のカルチャーモール「誠品生活(せいひんせいかつ)」です。
顧客を惹きつける偶然性には、必ずそれを生み出す「仕掛け人」が存在します。2つのブランドの仕掛け人やセレンディピティ戦略に迫り、AI時代に効果的な店舗集客の手がかりを探っていきましょう。
ライフスタイルの提案と社会貢献が融合した、宝探しのような空間
2009年にフランスの高級子供服ブランド創業者のコーエン夫妻が立ち上げた「Merci」は、パリでもひときわお洒落でトレンドの中心地、マレ地区にあります。織物工場を改装した3階建て1,500m²の店舗は大きな一軒家のようで、店前に停められた真っ赤なヴィンテージFIAT500が、買い物への期待を高めます。

「Merci」で有名なロゴ入りのカラフルなトートバッグをはじめ、店内にはホームリネン、家具、文具、書籍、ファッション、ビューティなど、ライフスタイルに関わるハイセンスなアイテムが、ジャンルを超えて幅広く取り揃えられています。
流行や季節に合わせ変化するアートのような洗練されたディスプレイも魅力的。「この家具をリビングに置いたら素敵……」「こんな本を探していた!」と、見ているだけで心が躍る、宝探しのような楽しい時間を過ごせます。
「Merci」には、コーエン夫妻の「これまでの成功への感謝を社会に還元したい」という思いが込められており、利益の一部は寄付に充てられます。顧客は、買い物を楽しみつつ、アイテムのセレクションなどから創設者の思いや社会的課題に触れられるのです。単に商品と出会うだけでなく、暮らしのエッセンスになる場所として、店舗が機能しています。
「偶然の出会い」のもう1人の仕掛け人は、店全体のクリエイティブを率いたアーティスティック・ディレクターのダニエル・ローゼンストロック氏です。彼は、シーズンごとの企画展示やディスプレイを通じて、Merci流のセレンディピティを築き上げ、お洒落なライフスタイルの提案と社会貢献を実現しました。
さらに、MerciはECサイトの閲覧・顧客データを活用し、「今、人々はどんなことに関心を持ち、何を求めているのか」を分析。実店舗に反映させることで、デジタル面からも「偶然の出会い」の創出を図っています。
2025年3月にはパリ市内に2号店がオープン。次なるセレンディピティを仕掛ける新たなステージへと踏み出しています。
デジタルを駆使した台湾発の文化発信拠点
一方、「誠品生活」は、1989年に創業者・呉清友(ロバート・ウー)氏が開いた「誠品書店」を原点に、2010年の分社化により誕生しました。
「Books, and Everything in Between.」(本とくらしの間に。)をコンセプトに、書店を軸としつつ、文具、雑貨、食品、ギフトなどの販売、さらにギャラリーや飲食店、ワークショップスペースなど複合的に組み合わせた文化空間を提供しています。
台湾国内のほか、香港や日本など海外にも展開し、それぞれ地域に根ざした文化発信拠点の役割も担っています。例えば、日本進出1号店の「誠品生活日本橋」の空間設計は、台湾の著名な建築家・姚仁喜(クリス・ヤオ)氏が、日本橋の歴史や江戸の精神から着想を得て手がけたもの。台湾や日本の文化を体験できるイベントや企画展示が日々開催され、買い物をしなくても両国の文化や新たな発見を存分に楽しめる工夫がなされています。

7月18日~8月24日の期間、「いつもの本屋に、音楽がやってくる。」誠品生活日本橋で「Summer Vibes ~本屋で夏フェス~」を展開(出典=PR TIMES)
誠品生活が仕掛ける「偶然の出会い」の大きな特徴は、「店舗を文化の発信拠点に」という呉氏の思いを投影し、店内全体をストーリー性の高い空間に演出していることに加え、デジタル技術やAIも駆使されている点です。
例えば台北・南西店では、音楽ストリーミング大手KKBOXと連携し、「AI歌単」(AIプレイリスト)機能を提供しました。これは、来店客が専用端末に今の気分やシーンを入力すると、その場でAIが最適な楽曲リストを生成し、店内BGMとして流してくれるもの。まるで自分のためだけに用意されたような空間での特別な購買体験は、大きな注目を集めました。
デジタル面では、自社の会員アプリから来店履歴や購買データを蓄積。誰がどこでどんな体験をしたか把握し、適切なタイミングで情報やクーポンを配信しています。デジタルなコミュニケーションとリアルな体験をシームレスに連携し、来店動機につなげています。
さらに外部のテック企業やアーティストとも協働し、新しい体験コンテンツを常に取り入れています。顧客は、いつ来店しても「新しい発見」と出会うことができ、買うものがなくても店に留まり回遊する。そうした仕組みが磨かれているのです。
「偶然」を演出するための、KPIへの効果的な落とし込み方法とは
Merciと誠品生活の事例からは、「偶然の出会いは、戦略的に設計できる」ことがわかります。これを自社の店舗ビジネスに導入する際は、「偶然の出会い」という曖昧な概念を具体的なKPIへ落とし込み、日々のマーケティングに組み込むことが重要でしょう。

一例として、運用の基本的な流れをご紹介します。
ゴールの定義とKPI設定
「偶然の出会い」によって向上させたいビジネス指標(回遊率、店内滞在時間、UGCなど)を明確にし、具体的なゴール(滞在時間を●分延伸したい、など)を設定します。
コンセプトの言語化
「関連性70%:意外性30%」の比率がポイントで、7割は顧客の期待に応えつつ、3割は「えっ!?」と意表を突く要素を差し込む設計で言語化します。
ミニマムな計測システムの構築
POSデータや特設棚のQRコードスキャン数、スタッフの定点観測など、大掛かりなシステムではなくシンプルなデータで効果を測れた方が、進捗確認など容易にできます。
役割分担の明確化
スムーズな進行のため「編集責任者(企画)」「実行担当者(MD/VMD)」「デジタル担当(CRM)」「現場担当(店舗スタッフ)」など、チーム内の役割を明確にします。
顧客データの取得とプライバシーへの配慮
顧客には「このQRを読み込むと〇〇の提案を掲示します」など、データ取得の目的を丁寧に伝え、信頼を損なわないようにします。
最初から多くのKPIを網羅する必要はありません。まずは「回遊率」のみに絞って計測をスタートし、顧客の動きが掴む。そのデータを念頭におきつつ、翌月は「店内滞在時間」まで拡張する、など徐々に指標を広げていくと無理なく運用が定着化するでしょう。
「偶然の出会い」を生み出すトリガー
Merciの季節ごとに変わるディスプレイや、誠品生活の体験イベントなど、「偶然の出会い」のトリガーの1つとなるのが、「意外性」です。
店舗の業種によりさまざまなアプローチがあると思います。例えば、以下のような企画は、大変な準備やコストも不要で、明日からでもすぐ実行できるのではないでしょうか。
70:30の棚
店内の主力商品を並べた棚に3割だけ、少し毛色の違う商品を混ぜて、意外性や宝探しのようなワクワクを創出。
スタッフの推しPOP
日替わりや週替わりで、特定の商品について3行ほどの推薦文をつける。その際、「誰にどんなことをなぜ薦めたいのか」まで伝えて、目を留めてくれた人の心を捉える。
音の演出
朝や日中はリラックスできるクラシック曲、夕方以降は元気の出るアップテンポ曲や大人っぽいジャズ曲など、顧客層に合わせた空間を作り上げる。
「偶然」から生まれる新しい価値
偶然の出会いは、老若男女いつでもワクワク楽しい気持ちになるものです。しかし、その出会いを「演出できる」という認識までは、持っていないマーケターも多いかもしれません。
Merciや誠品生活の店舗戦略を通じて理解できるのは、「今の顧客の気分に、どんな意外性のある提案ができるか?」という視点が大切で、どのような店舗でも新たな価値を創出できるということです。
もはや最適解はAIが即座に教えてくれるからこそ、アルゴリズムだけでは辿り着けないアイテムとの出会い、人の思いが介在する思いがけない発見や記憶に残る体験が、顧客の心を満たしてくれるのではないでしょうか。
Text:吉田裕美
●プロフィール
吉田 裕美(Yoshida Yumi) / フリーランス・ライター
1981年生まれ。金融機関での勤務を経て、2016年より現職へ転身。書籍、キャッチコピー、Webコンテンツ、プレスリリース、メールマガジン、コラムなど、様々なジャンルの執筆に携わる。近年は、サステナビリティや資産運用に関する記事制作も多数担当。