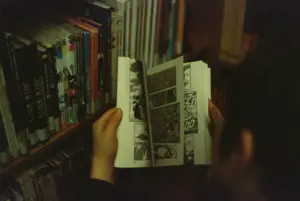「遊び」を軸に据えたブランド哲学
任天堂のマーケティング思想を語る上でまず触れたいのは、「遊びの本質」を最優先するという同社の揺るぎない哲学です。創業家出身である山内溥・元社長は「他社がやっていることはやらない」と公言し、社内に浸透させました。この路線はその後も受け継がれ、「ゲーム開発者は、自分が面白いと思うものを作るべきだ」という信念が定着しました。こうした哲学の延長線上に、「誰もが楽しめる体験」を届けることを使命としています。「子どもから大人まで」「コアゲーマーでなくても」楽しめる娯楽を追求し、世代やゲーム経験を問わず参加できる製品づくりに徹してきました。
その結果として、任天堂はスペック競争に走らず「体験価値」で勝負する独自の立ち位置を築いています。ゲームに馴染みのない人々でも直感的に遊べる操作系や、家族みんなで盛り上がるゲーム性を重視することで、時代を超えて新しいユーザー層を開拓。長期視点のブランド経営が脈々と続いているのです。

一貫性のあるブランド育成は、グローバルに事業展開を行うブランドの商業価値を測る「インターブランド」でも評価されています。最新版(2024年10月発表)において、任天堂は世界70位、日本企業としては5位にあたる115億ドル(約1兆6700億円)のブランド価値があると算出されました。これはあのパナソニック(世界98位・64億ドル)をも上回る評価額です。
こうした結果が多額の広告宣伝費用に頼った結果ではないことは、数字が示しています。2025年3月期の任天堂の広告宣伝費は865億円と、売上高1兆1,649億円、営業利益2,826億円と比較して、極端に大きな額ではありません。
遊びの共有を促すデザイン:囲い込まない戦略
任天堂の哲学が顕著に表れるのが、ユーザー同士の「遊びの共有」を促すゲームデザインです。一般的にエンターテインメント業界では、ユーザーを自社プラットフォーム内に囲い込み、他者と共有させないことで個々の売上を最大化しようとする戦略が取られます。ゲーム業界においては、オンライン対戦やダウンロードコンテンツ販売で一人ひとりから収益を得るのが定石なのです。しかし任天堂は対照的に、「みんなで遊ぶ」体験そのものに価値を置き、結果として自社のファンコミュニティを拡大する道を選んできました。
1990年代には、ゲームボーイに通信ケーブルを繋いで友達と対戦する——そんな光景が当時は公園や学校で日常的に見られました。子どもたちは互いに協力し合い、情報交換し、時にはソフトを貸し借りしながらプレイしました。そうした仕掛けが一種の文化や社会現象を生み出したのです。
「マリオカート」や「大乱闘スマッシュブラザーズ」といった看板タイトルに代表されるように、任天堂は早くから「1つの画面をみんなで囲んで遊ぶ」スタイルを重視し、Nintendo 64時代にはコントローラー4つ差しを標準装備するなど、ハード面でもサポートしてきました。
ニンテンドーDS/3DSでは「ダウンロードプレイ」という機能を搭載し、ソフトを持っていない友人でも一緒に対戦や協力プレイができるようにしました。プレイヤー全員にソフトを買わせたいところを、あえて未購入者にも門戸を開く設計にしたのです。これは短期的には販売機会を手放すようにも見えますが、実際には「友達と遊んでみて面白かったから自分も欲しくなった」という新規ユーザー獲得に繋がりました。
任天堂はユーザー自身をマーケティングの担い手(伝道師)にしてしまうのが上手なのです。「他人の喜ぶ姿を見るのがいちばんの快楽」という、故・横井軍平氏(ゲームボーイ生みの親)の言葉を体現する仕組みです。横井氏はゲーム設計におけるコミュニケーションの重要性を説き、「ゲーム機やソフトを持ち寄って遊ぶ」文化を生み出しました。任天堂の数々のアイデアには、この「遊びは人と人を繋ぐもの」という思想が脈々と流れているのです。
「囲い込み」から「おすそわけ」へ:デジタル時代の挑戦
任天堂の「遊びの共有」思想は、デジタルビジネスの領域にも進化して表れています。その象徴的な例が、2025年に発表されたNintendo Switch 2の「バーチャルゲームカード」機能でしょう。これは端的に言えば、デジタル版ゲームソフトの貸し借りを可能にする仕組みです。自分がダウンロード購入したソフトを、Nintendoアカウントのファミリーグループ内のメンバーに最大14日間まで貸し出すことができます。
「データを借りた側」はそのゲームを期間中プレイでき、「貸した側」はその間そのゲームを遊べなくなる。この仕組みは、デジタル時代において失われがちな「ゲームの貸し借り文化」を復活させるものとして注目されました。

業界全体を見渡しても公式にデジタルゲームの「一時シェア」を認めた事例は極めて珍しいと言えます。なぜ任天堂はこのような大胆な施策を打ち出したのでしょうか。他社であれば「デジタルソフトは一人一ライセンス購入が当たり前」です。実際、多くのプラットフォームはアカウント連携やDRMでがんじがらめに固めています。しかし任天堂は違いました。カセットやディスクの時代に、友達同士でゲームを貸し借りする世代からの、「面白いものは人に薦めたくなる」という真理を理解しているからこそ、あえて公式に「おすそわけ」できる場を設けたのです。
「任天堂ならではの親切な仕組み」として、発表当初このニュースはSNS上でも大きな話題となり、「任天堂らしい」「ユーザー想いだ」といった声が多く聞かれました。ブランド好感度を高める効果は計り知れません。
思想が生むブランド体験とファンコミュニティ
マーケティング的に見ても、任天堂のアプローチは極めて理にかなっています。ユーザーが自発的に製品を周囲へ広めてくれるため、広告に頼らない強力な口コミ効果が生まれます。実際、WiiやニンテンドーDSが爆発的ヒットとなった背景には、「家に集まった親戚や友人がプレイして盛り上がり、その場でファンが増えていく」という現象がありました。任天堂は「遊び」そのものを広告媒体に変えてしまったと言えるでしょう。
また、ユーザーとの長期的な関係構築にもこの思想は寄与しています。任天堂は決して品質を犠牲にして短期利益を追求したりしません。常にコンテンツのクオリティと体験価値を保証し、「任天堂のゲームなら安心して楽しめる」という信頼を守り抜いています。
子どもの頃に家族で遊んだマリオの思い出が、大人になって自分の子どもにスーパーマリオを買い与える動機になる——任天堂は世代間で共有される体験を創出することで、他社には真似できないブランド循環を生み出しているのです。
「遊びの楽しさを届ける」ことにフォーカスした任天堂の戦略は、結果的に格段の市場拡大と収益をもたらしました。たとえば「ゲーム人口の拡大」を掲げ、WiiやDSでシニアや非ゲーマー層を取り込み、大きなブルーオーシャンを開拓しました。
マーケティングの教科書的に言えば、任天堂は「競争」より「共有・安心・創造性」に軸足を置いたセグメンテーションを行い、製品ポジショニングでも「勝ち負けではなく、みんなで遊ぶ時間と思い出」を提供するブランドとして差別化してきたのです。マーケティングの価値観自体を転換してみせたとすら表現できます。

遊びの思想が導くマーケティングの未来
任天堂の事例は、マーケティングにおいて「何を売るか」以上に「何のために売るか」が重要であることを物語っています。
人々に届けたい価値や意味が明確であれば、それに沿って売り方や戦略も大胆に設計し直すべきでしょう。任天堂が示したように、思想とマーケティングが結び付いたとき、ブランドは単なる商品以上の文化や体験を社会に提供できるのです。単にモノを売るのではなく、思想や物語を共有する——そんな在り方こそ、これからの時代に求められるのではないでしょうか。
Text:田中誠司
●プロフィール
田中 誠司(Tanaka Seiji) / PRストラテジスト、ポーリクロム代表取締役、PARCFERME編集長
自動車雑誌『カーグラフィック』編集長、BMW Japan広報部長、UNIQLOグローバルPRマネジャー等を歴任。1975年生まれ。筑波大学基礎工学類卒業。近著に「奥山清行 デザイン全史」(新潮社)。モノ文化を伝えるマルチメディア「PARCFERME」編集長を務める。